
アイスランドでの昭和基地とのオーロラ共役点観測の始まり
フランスとの共同観測 私が国立極地研究所に職を得て最初に関与した研究プロジェクトは、1976年〜1979年に行われた国際磁気圏研究計画です。極地研が担当するこの研究プロジェクトの一つが共役点観測であり、昭和基地とアイスラ…

フランスとの共同観測 私が国立極地研究所に職を得て最初に関与した研究プロジェクトは、1976年〜1979年に行われた国際磁気圏研究計画です。極地研が担当するこの研究プロジェクトの一つが共役点観測であり、昭和基地とアイスラ…

クラッシックな会場から出て、200~300メートルくらい歩いたところにランチ会場のレストランが用意されていました。 デザートにはエスプレッソと合うようなマカロンやムースがでました。しっかりしたものを食べるというより、軽め…

大学と大学院 物理に全く興味の無かった私が、山形大学1年生の教養時代に受けた物理の講義(特にニュートン力学)が素晴らしく、生まれて初めて自ら積極的に参考書をむさぼり読み、知識を得る喜びを味わいました。2年生からは物理学科…

今回は、壇上に上がってひとりひとり専門のことを発表する会議ではなく、4~5人が壇上に上がって、司会者が質問したり会場から質問を受けたり、自己紹介的な発表をしたりしました。班ごとに議論することが多かったですね。どの班(興味…

北極や、南極だけをテーマにした会議やシンポジウムは数多く開催されていますが、「両極」をテーマにしたシンポジウムはなかなか無いのです。今回のシンポジウムでは、北極と南極に共通する課題や特徴、また南極と北極で大きく異なる考え…

地球温暖化や環境変化など、どう取り組んでいこうかという話になると、まず真っ先に出てくるのは国際協力なんですよね。今回のシンポジウムでも、いろんなテーブルで話題になりました。 例えば、インフラの整備や、基地、船、人工衛星な…

今回のシンポジウムのテーマは「極域科学に対する、将来の共同研究を考える」。若手も含めて、何が課題で何をやるのか考えようということでした。 実は、両極の25年ごとの活動であるIPY(国際極年)が2032年にくるので、ここへ…
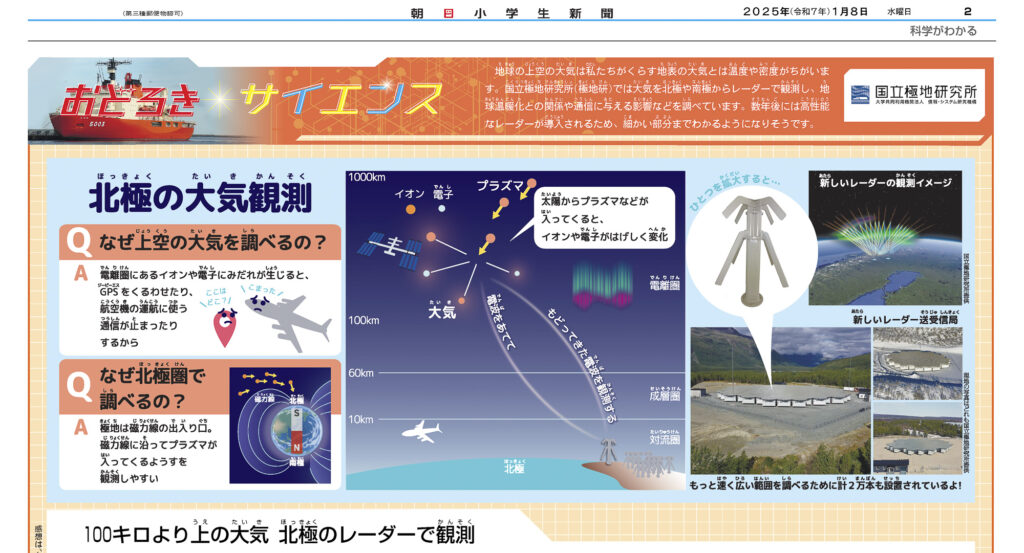
話者:小川泰信(宙空圏研究グループ教授 ) PDFはこちらからダウンロードいただけます。

2024年2月22日と23日にモナコで、極地変化に関する科学のシンポジウム「北極から南極へ」の第2回目のシンポジウムが開催されたので参加してきました。2022年に、現モナコ公のアルベール二世(在位2005年7月12日~)…