南極や北極の研究者を目指すなら、どの大学院を選びますか? 日本にはいくつかの選択肢がありますが、その一つが「総合研究大学院大学(以下、総研大)」の「極域科学コース」です。総研大は、日本の研究機関が連携して構成する大学院大学で、最先端の施設を活用しながら研究を進めることができます。極域科学コースでは、南極・北極に関する幅広い分野を学び、研究者としての視野を広げることができます。極域科学コース長、在学生によるリレー連載形式で、極域科学コースを紹介していきます。
なぜフィールドに出るのか
北極や南極のフィールドは寒冷な厳しい環境であり、そこへ行くにも日数がかかります。それでもなお、「フィールドサイエンティスト」を養成しようとしているのが総研大の極域科学コースです。
今や、そんな厳しいフィールドへ行かなくても、観測は人工衛星や自動観測装置に任せ、日本からネットでデータにアクセスしてデータを取得すれば良いのではと思う人は多いと思います。私も海の観測に人工衛星を使う研究者の一人であり、極域に行かずしてできる研究はあります。しかしながら、やはりフィールドに出て、実際にデータを取ることは重要だと考えています。
私が今の研究を始めたのは修士課程1年生の夏頃。その当時、経済大国であった日本は大型の地球観測衛星を打ち上げる準備中でした。その衛星に搭載予定のセンサーのひとつが海の色を観測するセンサーで、アメリカと日本のどちらが先に打ち上げるかという競争がおきていました。私が博士課程に進む頃には衛星が打ち上げられるという話もあり、そのセンサーで色々なものを推定するための基礎研究に興味を持ち、私のフィールドサイエンスが始まりました。その後、毎年のように船でフィールドに出て、博士課程1年生の時には南大洋(南極海)の観測に参加する機会に恵まれ、今の仕事に繋がっています(写真1)。
なぜ衛星なのにフィールドサイエンスなのかと言うと、衛星で何かを推定するには、まずは現場で衛星と同じ物理量(私の研究の場合は各波長の光の強さ)と推定の対象となるパラメータ(私の研究の場合は植物プランクトンの量や生産量)を実際に測定する必要があるのです。その現場データを元に作成した関係式に衛星データを入れると、JAXAやNASAのウェブサイトで見るような衛星画像が出来上がるという仕掛けです。

このような研究をしていると、過去の論文と自分のデータを比べて、データがちょっとおかしい? と思うことがあります。その原因を探るには、フィールドで実際に経験したことが役立ちます。フィールドでは天候が悪く海が荒れたり、観測装置が不調であったり、思ったように実験が進まないことは良くあります。特に北極や南極では曇っていたり、氷があったりと、悪条件が重なります(写真2)。

研究しているフィールドで起こっていることは、実際に行って自分で見ないと直感的にわからないことが良くありますので、その状態とデータを結びつけることで、何に原因があるのかを探ることも可能になります。自分の研究対象がどのように変化しているのかも、自分で見るか遠隔で見るかでは大きく異なると思います。フィールドへ出れば、氷山や海氷が多いのか少ないのか、海が荒れているのか静かなのかも、身を持って感じられますし、そこから新しい研究のアイディアも生まれるかも知れません。そして何よりも、自分で、その場で取ったものは推定ではなく、リアルな試料やデータであり(もちろんエラーやミスがなければですが)、現実の姿をそのまま表しているのです(写真3, 4)。


さらに、フィールド観測へは多くの場合、さまざまな分野の人と一緒に出かけますので、他の分野の研究やデータをリアルタイムで見ることもできますし、自分では思いもしないアイディアをもらうこともあります。そのような体験は、自分が固執していた考えや、自分の分野での固定概念にとらわれず、より広い視点で研究を進めるチャンスにもなります。北極や南極を研究したいと思っている皆さん、極域科学コースに進学し、一緒にフィールドへ行きましょう!
【連載】総研大「極域科学コース」って?(全4回)
前の記事|「極域科学コース」はどこの大学? https://kyoku.nipr.ac.jp/article/3327
次の記事|第3回は、現役の総研大学生による寄稿です。6月12日の公開を予定しております。お楽しみに!
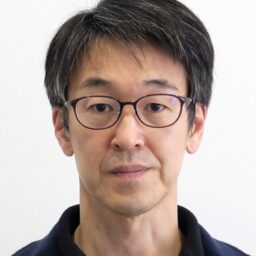
- 平譯享(ひらわけ とおる)
- 国立極地研究所 生物圏研究グループ教授。2022年度より極域科学コース長。北海道出身。専門は海洋光学と衛星海洋学。海の光と植物プランクトンの量や種類との関係を現場で調べ、衛星観測に応用して南極・北極海域の長期変動を研究している。南極海と北極海を含む多くの調査航海に参加。第42次南極地域観測隊越冬隊に参加。

