南極や北極の研究者を目指すなら、どの大学院を選びますか? 日本にはいくつかの選択肢がありますが、その一つが「総合研究大学院大学(以下、総研大)」の「極域科学コース」です。総研大は、日本の研究機関が連携して構成する大学院大学で、最先端の施設を活用しながら研究を進めることができます。極域科学コースでは、南極・北極に関する幅広い分野を学び、研究者としての視野を広げることができます。極域科学コース長、在学生によるリレー連載形式で、極域科学コースを紹介していきます。
南極や北極の研究者になりたい!
……と思った皆さん、どこの大学院を目指しますか?日本には極地の研究を行っている大学はいくつかあると思いますが、その一つが「総合研究大学院大学(以下、総研大)」の「極域科学コース」です(https://www.nipr.ac.jp/soken/)。

ところで、極域科学コースの前の「総研大」とは何?と思った方も多いでしょう。南極や北極の研究を行っている研究室所属の学生さんであれば、聞いたことがあるかも知れませんが、知らない方が大多数であると想像します。そんな総研大なのですが、日本の大学共同利用機関(国立の研究所など)が連携して構成する大学院大学であり、それら研究所の最先端の施設を利用して研究することができます。教員は各研究所の研究者ですので、今まさに研究所で行なわれている研究に触れながら一緒に研究することができます。
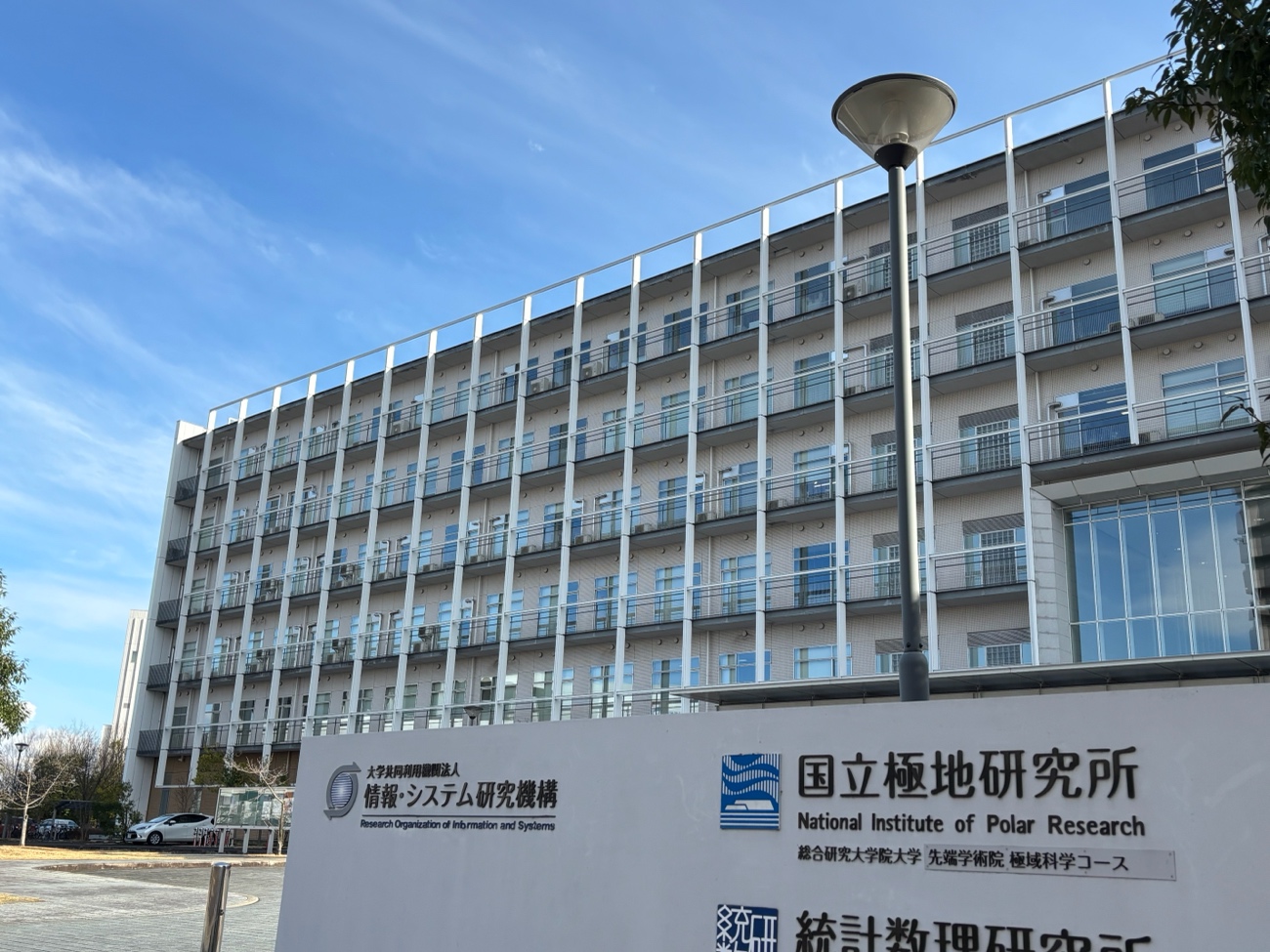
さて、本題の「極域科学コース」は、南極・北極の観測や研究を推進している「国立極地研究所(極地研)」を基盤機関とする総研大のコースの一つです。極地研にいる研究者はもちろん全員が南極や北極の研究者であり、寒冷な極域の自然現象解明に寒さも忘れて没頭する人が沢山おります。研究分野は一つの研究所としては大変幅広く、オーロラから大気、雪氷、海洋、海氷、岩石、隕石、地質、生物にまで及びます。極域科学コースに入学した学生さんは自分の専門分野の研究を最先端の設備を利用して進めることができますし、同時に他分野の講義や指導も受けられますので、研究者としての将来に向けて知見を広げることが可能です。
そして何よりも、実際に北極や南極のフィールドへ出かけ、自分自身でサンプルやデータを取れる「フィールドサイエンティスト」を養成することが極域科学コースの大きな目的の一つです。実際、コース在籍中に日本南極地域観測隊や北極観測に参加し、取得したデータを使って学位(博士)を取得し、さらに修了後も、学生時代に習得したフィールドサイエンティストの力量を活かし、国内外の大学や研究所で極域研究者として活躍されている人が多数おります。
このように、総研大の極域科学コースは、南極・北極の研究をするには絶好の環境です。南極や北極のフィールドサイエンティストになりたいと思った皆さん、是非本コースへの進学を検討して下さい。

【連載】総研大「極域科学コース」って?(全4回)
次の記事|フィールドサイエンティスト https://kyoku.nipr.ac.jp/article/3440
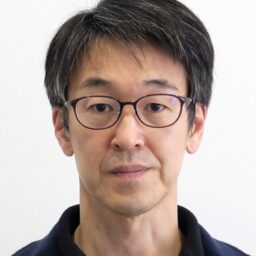
- 平譯享(ひらわけ とおる)
- 国立極地研究所 生物圏研究グループ教授。2022年度より極域科学コース長。北海道出身。専門は海洋光学と衛星海洋学。海の光と植物プランクトンの量や種類との関係を現場で調べ、衛星観測に応用して南極・北極海域の長期変動を研究している。南極海と北極海を含む多くの調査航海に参加。第42次南極地域観測隊越冬隊に参加。

