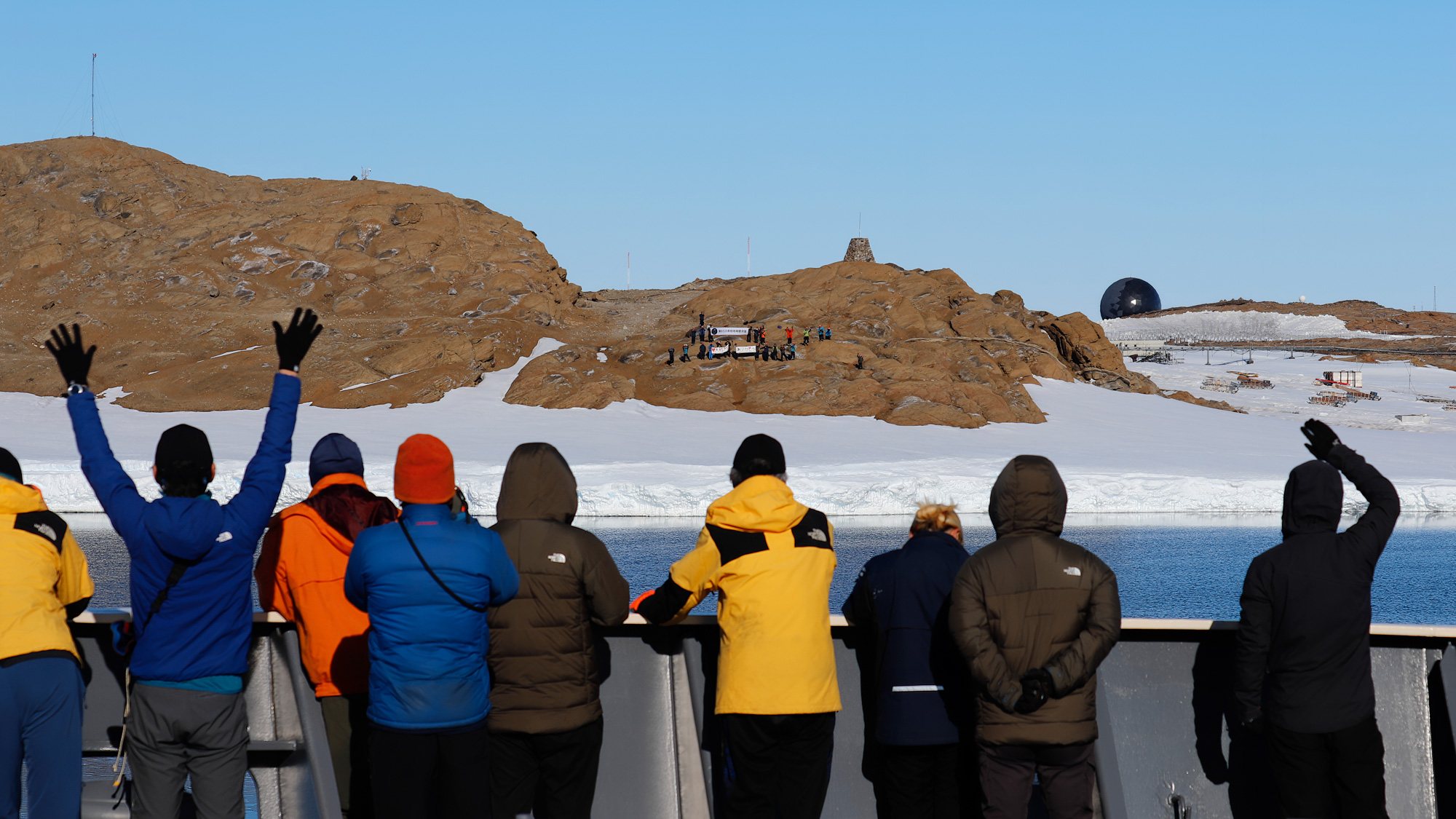南極地域観測隊の広報として、自身の持ち味を活かし、読んでくれた人の心に残る記事を書きたい——。丹保俊哉・第65次南極地域観測隊広報隊員は、南極での4ヶ月間、広報として「観測隊ブログ」を日本へ届けることに奮闘してきました。発見、驚き、そしてちょっとした苦労話。伝えたいことは山ほどあるのに、記事にできなかったこと、書ききれなかったことばかり。当時伝えきれなかった南極の情景を、赤裸々な心理描写を交えて、振り返ります。
尊敬し助け合える関係性
65次夏隊の広報隊員がお伝えしてきた連載の最後は、観測隊そのものについて触れたいと思います。
観測隊を構成している隊員・同行者は、一人ひとりが産官学の各分野から研究者、技術者たちが本来の所属先で選出されるか、隊員公募に応じて選ばれたエキスパート、プロフェッショナルたちです。広報隊員も選ばれていることは確かですが、必ずしも広報活動のエキスパートという立場でもない自分にとって他の隊員たちは一様に眩しい存在でした。みんなきっと多くの成果や達成目標を目指して自身の調査や業務に集中したいだろうし、わざわざ広報の取材を受ける余裕なんてないだろうなぁとなかなか声を掛けづらく、自分自身の職責をうまく果たしていくことができるのだろうかと、毎日戦々恐々としていました。タイミングを見計らって今なら大丈夫そうだ! と、思い切って隊員たちに接してみると思いのほか、皆身構えることもなく気さくで平易に解説してくれるし、作業に集中していたときには後から時間を取って丁寧に対応してくれることもあって、毎回ホッとしたものでした。何のことはありません。私以外の隊員や同行者の皆は、それぞれが抱える業務の必要性を理解し相手にも敬意を払おうとする気持ちを実践していただけで、私自身が同じ観測隊員であるということに無意味な気後れがあって、一方的に壁を感じつづけていただけでした。数えること65回にもなった南極観測事業の意義は、国内での訓練を経て老いも若きも関係なく皆理解し、それぞれが背負う業務の重みは互いに支え合って乗り切ろうという共通した意識が醸成されていたのでしょう。とてもありがたく感謝しつつも自分の心積もりのなさに恥ずかしさを覚えつつ、四苦八苦しながら観測隊ブログを書いたものです。

調和する個性の集団
このように私が南極観測隊員の集団に感じたのは、観測事業の維持や継承という大きな目標に向かって互いに協力し合って高い調和性を発揮する能力を持ち合わせているということでした。全国から高い職能と信念を持った十人十色の個人が集合する観測隊は、ともすれば足並みが揃いにくい場面も現れるのではないかと密かに邪推したものですが、隊員の選出に当たって協調性がとても大切にされた背景があったのでしょう。また調和を図るべく表に裏にと働き続けた橋田隊長や行松越冬隊長、庶務隊員、設営をはじめとする各チームリーダーのたゆまぬ努力も伺えました。
職住環境が同居している観測隊員たちはちょっとした暇や就寝前に、「しらせ」の寝室や第二夏期隊員宿舎(二夏)の談話室などに集まり歓談します。お互いや隊内の仕事の進捗状況などについて情報交換するシーンでは、ブリザードが接近し外出制限が発令されたことで、設営やヘリ空輸の計画に遅延が生じ、さらには野外観測チームの活動にも影響していることなどのやるせない気持ちを吐露しあい、殺伐とした雰囲気が広がることがしばしばありました。私自身、予定していた野外調査の取材が流れてしまったり、筆力不足で言葉が紡げず、思うようにブログを発信できないことでストレスを溜めることには事欠かなかったのですが、そうしたどうしようもない気持ちをうち明けても建設的じゃないという考え方から、内に秘めてしまう性格をしています。一方であけすけに語り合うことで気持ちを発散させるカタルシス効果や自己明確化の効果があったのでしょう。互いの親密さを深め、ストレスを小さなうちに解消させて毎日活き活きとしている隊員たちの様子をみて、個性を消さずにそれぞれが輝いている観測隊って強いメンタル性と優れたバランス感覚を持ち合わせる凄い集団だなあと内弁慶な自分は羨望していたものです。


集団の個性
また個別の観測隊にも、それぞれの個性があるようでした。それは過去の隊次の逸話を耳にしたり体験録を読んだりして感じたことですし、私が直接感じることができたのは65次隊と、昭和基地上陸以降に接してきた64次越冬隊だけでしたが、やはり随分と隊の印象は違うものだなぁと感じました。それは極地での越冬という実経験を経て環境に適応したことで生じる団結力や認識の相違から醸成されるためであろうか、と2隊を比べながらしばしば歓談のネタにしたものです。とはいえ越冬隊と夏隊の個性が大きく違っても当然といえそうです。私の狭い視野で観察した範囲での捉え方ではありますが、夏期オペレーション(夏オペ)は短期間に成果を出す必要があり、観測系・設営系はそれぞれに予め練られた作戦に基づいた八面六臂の動きをする個別のチーム戦になるためか、隊員たちの個性が強く表れている印象を持ちます。その夏オペを縁の下の力持ちとして全力でサポートするべく、飛行作業を中心とした日程と隊員の行動を管理するのが夏隊長のとても大変な役割のようでしたが、それ故に隊の印象は隊員全員によって醸成されていると感じたのでしょう。一方で、冬期の極限環境の中で長期戦を独力で戦い抜く必要のある越冬隊では、隊の安全を背負わなければならない越冬隊長の権限が大きく、越冬隊長の個性が色濃く隊全体に波及し、またいわば命を預ける形になる越冬隊員にとって最も頼りとする越冬隊長との間で強く信頼しあっている印象が生まれることも想像に難くないものでした。

観測隊は具材が調和するおでん鍋
私自身が体験した夏オペを通して、観測隊の特長をうまく表現し多くの人にその魅力を分かりやすく伝えられる例えは何だろうかと考えて思いついたのは「おでん」です。おでんの魅力は、さまざまなおでん種が出し汁で煮込まれ、それぞれの個性を持ちながらも、全体としてまとまりがある点です。色んな種類の具材を寄せ集める鍋料理の中でも、全体が調和している料理の筆頭はおでんではないでしょうか。少なくとも卵と大根が調和する鍋料理なんておでん以外に思いつきませんでしたし、みんなが主役の料理もおでんの特長ではないでしょうか。異論反論は認めます(笑)。これまでにはすき焼きやちらし寿司などといった料理で表せられる個性を持つ観測隊もあったかもしれません。ですが、65次隊を表すにはおでんがしっくりくるかなと感じました。南極という鍋の環境で、夏隊長が出し汁として全体の旨味、個性を生み出すものの、具材に例えた隊員達の個性は埋没することなく活き活きと調和していました。
越冬を体験することなく帰国した夏隊広報ではありますが、仮に越冬隊の特長を同じく料理に例えるとすれば、出し汁がより大きな役割を果たす「茶碗蒸し」でしょうか。さてこれらを賞味するのは一体誰になるんでしょうね。
伝えたかった極地の姿形を5回に分けて記事にさせていただきましたが、自分の稚拙で筆力のなさに限界を感じてしまいましたし伝えきれなかったことがまだあって反省しきりです。今は本業である学芸員として、どんなアイデアを使えば極地の姿形をより分かりやすく、より心に響くよう伝えられるだろうかを模索しています。その成果が博物館の展示物となって皆さんの目に留まる機会があれば幸いです。ここまでお読みいただきありがとうございました。<【連載】伝えたい極地の姿・形(完)>

【連載】伝えたい極地の姿・形(全5回)
前の記事|露岩域はシマシマワールド! https://kyoku.nipr.ac.jp/article/3472
-256x256.jpeg)
- 丹保俊哉
- 富山県立山カルデラ砂防博物館の学芸員として立山連峰の地震や火山活動などの調査をおこないながら、山地の成長とともに発達した地形の生態系や地域社会との関わりを紐説いて、立山の魅力と脅威を平易に普及啓発することに取り組んでいる。色々な地形をみてその成り立ちを妄想するのが好き。第65次南極地域観測隊広報隊員。ぼっち気質のため、南極では昭和基地よりも露岩域の方が過ごしやすかった。